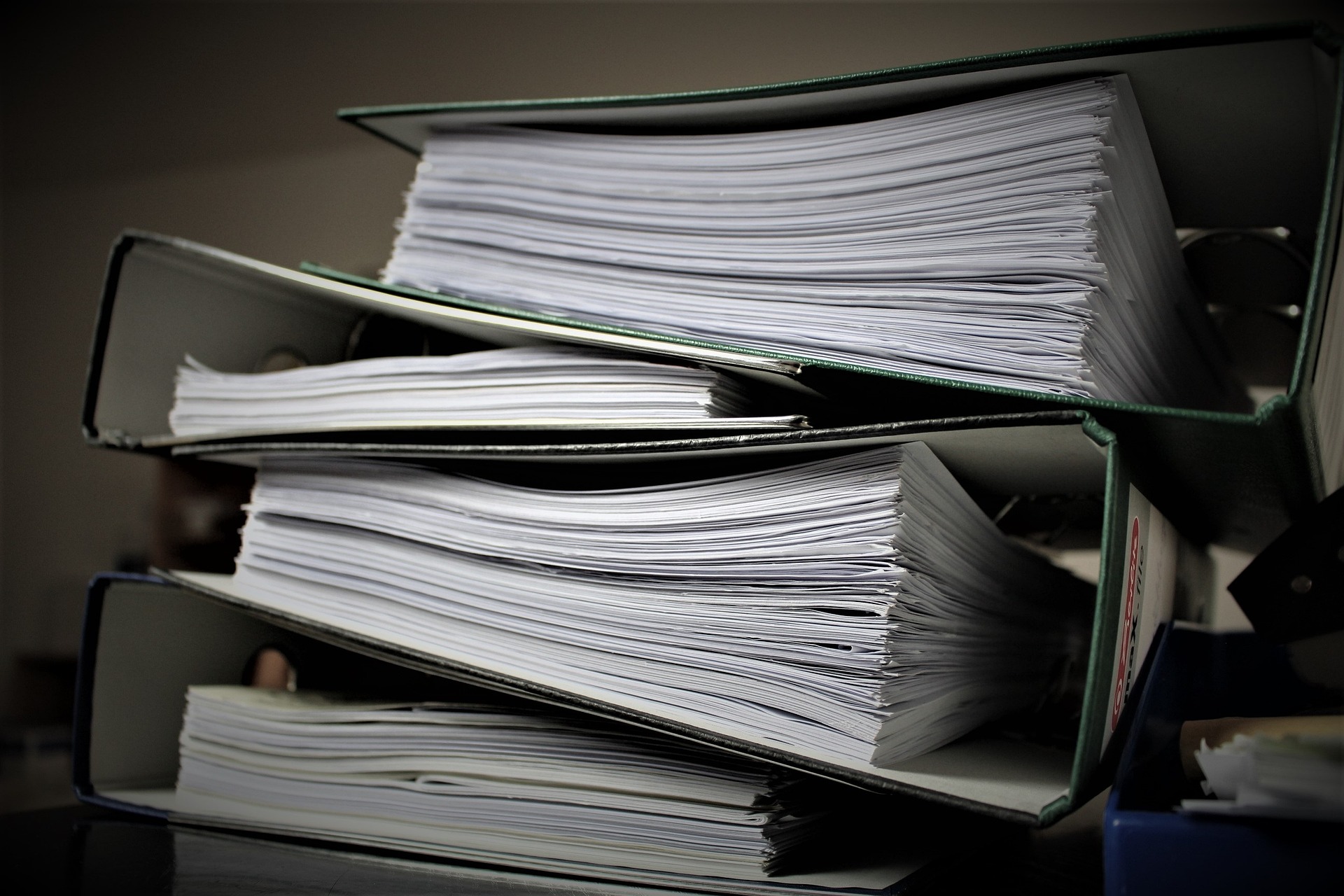コラム
公開日
M&Aにおける人事労務上の対応について再考する
多田国際コンサルティング株式会社
フェロー 佐伯克志
近年、日本国内におけるM&Aの件数は増加傾向にあり、2024年には前年より11%増加し、4,074件(レコフ調べ)と過去最多を記録しました。特に、後継者不在を理由に事業売却を希望する企業は、今後も増加すると見込まれています。
人事労務の専門家として、M&Aにおけるデューデリジェンスや統合後の戦略検討などをご支援する中で、さまざまなケースに直面します。
あるケースでは、当初は合併を予定していましたが、事前の検証により両社の基本給の格差が大きく、給与水準を高い方に合わせると人件費が大幅に増加し、慢性的な赤字体質に陥ることが判明。結果として合併は見送り、業務提携へと方針転換されました。
両社の経営者は労働条件の整合にほとんど関心がなく、漠然と「なんとかなる」と考えていたようですが、状況を可視化することで、合併後の現実が明確になり、判断を変えるに至ったのです。
こうした経験から今回は、M&Aにおける人事労務の留意点について、改めて考えてみたいと思います。
1. 一つの会社に十数種の就業規則と給与規定が併存していたら
正社員の就業規則や給与規程が10種類以上あり、労働条件はもちろん、基本給、手当の種類、昇給・昇格のルール、人事評価制度などがすべて異なる状態のため、これを集約したいというご相談を受けたことがあります。皆さんの会社がこのような状況だった場合、どのような混乱が生じるでしょうか。
まず、勤怠管理や休暇制度の運用が複雑になり、基本給や手当のルールの違いにより給与計算も複数のパターンに対応しなければなりません。また、人事評価や昇給・昇格の時期や方法も制度ごとに異なり、非常に煩雑です。そのため、この会社では人事労務部門に多くの人員を配置して対応していました。
この会社は、短期間で十数回のM&Aを行い、規模を急拡大した結果、制度統一が後回しとなっていました。事業特性上、人事異動があまり重要ではなかったため、就業規則等の一本化よりM&Aの実行を優先したのです。
しかし、市場環境の変化を受けて店舗再編が必要となり、人材流動性を高めるため労働条件の統一化に取り組むことになりました。現状分析の結果、制度統一のためには数千人の社員に対し不利益変更への対応が必要であり、交渉には膨大な時間とコストがかかるうえ、離職リスクも高まることが判明し、計画は頓挫してしまいました。
2. 目指すべきは人事労務に関するルールの統一
M&Aでは、吸収合併のように一つの会社に統合する場合もあれば、グループ会社として存続させる場合もあります。一つの会社に集約する場合はもちろんですが、グループ会社として存続させる場合であっても、本社としてグループガバナンスやグループ内での人材の柔軟な活用、人事労務に関する業務の効率化を考えると、可能な限りルールを統一しておく、あるいはルールのフォーマットを統一しておくことは重要です。
そこで、「人事労務に関するルールの統一」を目指すべき姿として、M&Aのプロセスにおいて取組むべき事項について確認していきましょう。
3. 平時に行うべきこと
「M&A先の就業規則や給与規程が、自社よりも精緻だったため、あわてて自社の制度を見直した」というクライアントもいます。合併された側の社員が新しい制度を見たとき、その内容が稚拙であれば不満や不信感が生じかねません。
制度を統一するには、可能な限り自社の制度を相手先に受け入れてもらう必要があります。そのためには、日頃から自社の制度を整備し、説得力ある内容にしておくことが大切です。
また、M&Aを経営戦略の一環として積極的に行う企業であれば、事前に統一すべき項目と変更可能な項目のフォーマットを決めておき、それに基づいてM&A後の制度を整えることができるようにしておくべきです。
4. M&Aの各段階で行うべきこと
① デューデリジェンスで行うべきこと
M&Aでは、財務・法務・労務の観点からデューデリジェンス(DD)を実施します。労務DDでは、労働債権の有無や法令遵守状況にとどまらず、就業規則等や給与制度、人事評価制度についてフィットギャップ分析を行うことが重要です。
給与に関しては、基本給、所定内給与、月給、賞与、年収などを比較し、水準差を把握しておく必要があります。制度がルール通りに運用されているかも含め、可能であれば過去の運用実績の証跡も確認しましょう。
こうした分析により、制度統一に向けた課題を洗い出します。たとえば、存続会社の給与水準が高い場合、それに消滅会社の給与を合わせると人件費が増加する可能性があります。逆に、存続会社の給与水準が低い場合、消滅会社の給与を下げることで優秀な人材の離職を招く可能性があります。
これは給与に限ったことではなく、福利厚生、休暇制度、労働時間など全般に言えることです。
当然ですが、相手先の優れた人材離職を防止するためには、これらの条件を合併前と同じにするか、より高い水準にしなければなりません。
こうしたことを前提として、合併後の対応について検討します。もし給与等の条件を統一することが人件費の大幅増につながり、合併のシナジー効果を大きく毀損するような場合は、合併以外の方法についても検討する必要があります。
② 合併契約書作成前に行うべきこと
労働契約承継法では、吸収合併や新設合併において、「消滅会社の労働契約は包括的に承継されると定められており、それぞれ被合併会社、消滅会社の労働契約は、包括的継承することとなっているため、原則として変更はできない」とされています。また、労働契約法第9条、第10条においても、合併を理由に労働条件(賃金、労働時間・福利厚生など)を一方的に不利益に変更することはできないとなっています。
しかしながら、合併後に複数の制度が併存するのは現実的ではありません。そこで不利益変更の有無に関わらず、労働条件の変更が必要となる場合には、その旨を合併契約書に記載することが求められます。
ただし、労働条件の変更について不利益変更の可能性があるにもかかわらず、例えば「合併後も、消滅会社に所属していた従業員の雇用関係は存続会社に承継され、現行の労働条件(賃金、職務、就業場所等)は原則として維持されるものとする。」といった内容を安易に記載することは、あとになって変更の障害となりかねません。
そのためには、労務DDの際に実施した「人事労務に関するルールに関するフィットギャップ分析」の結果をもとに、どういった労働条件についてどの程度見直す必要があるのか、消滅会社と存続会社のどちらの制度を活かすのか、あるいは新たな制度を整備するのか、不利益変更となる可能性の高い項目はどれで、どの程度なのか、といったことを両者で協議したうえで、合併後に人事労務に関する各種制度を統一するための移行計画を作成します。これをもとに、必要な事項を合併合意書に記載するのです。
③ M&A後に行うべきこと
M&A後は、合併契約時に策定した移行計画に基づき、労働条件の移行を進めます。不利益変更の有無にかかわらず、対象社員に対して変更理由や内容、経過措置を丁寧に説明することが必要です。
重要なのは、合併後の社員全員が「同じ会社の社員として、同じルールが適用される」という意識を共有できることです。消滅会社出身の社員が不利に扱われるようでは、制度への理解と納得を得ることはできません。
そのためには、従業員代表との協議や説明会の実施、相談窓口の設置、個別面談の実施など、丁寧な対応が求められます。特に給与に関しては、減額による離職を防ぐため、「調整給」や「経過措置」を活用することで、ルールの統一を図りつつも、緩やかな移行を図ることが効果的です。当然ですが、内容によっては個別同意の取得が必要になることもあります。
5. 売却側として取り組んでおくべきこと
10年以上前になりますが、あるクライアントから人事労務に関する制度全般の見直しを依頼され、就業規則等の改定、労働時間管理の精緻化、人事制度の刷新をご支援しました。
このクライアントの創業経営者は、全ての制度の見直しを終え、運用を開始してから約2年後、この企業を大企業に売却しました。
後日、この経営者から「人事労務に関する制度を整えたうえで会社を譲渡することは、企業価値の向上はもちろん、これまで貢献してくれた社員への責任を果たすことになった」との言葉をいただきました。
これまでM&Aで「買う側」の視点が中心でしたが、「売る側」においても売却前に人事労務に関する制度を整備しておくことは、企業価値の向上、そして社員の将来への配慮という観点から、非常に重要な取り組みであるといえるでしょう。
多田国際コンサルティング株式会社では、人事制度設計、定年延長といった制度設計はもちろん、今回ご紹介しましたM&Aといった経営戦略における人事労務面でのご相談にも対応しております。お気軽にご相談ください。